リスクの正体を理解する
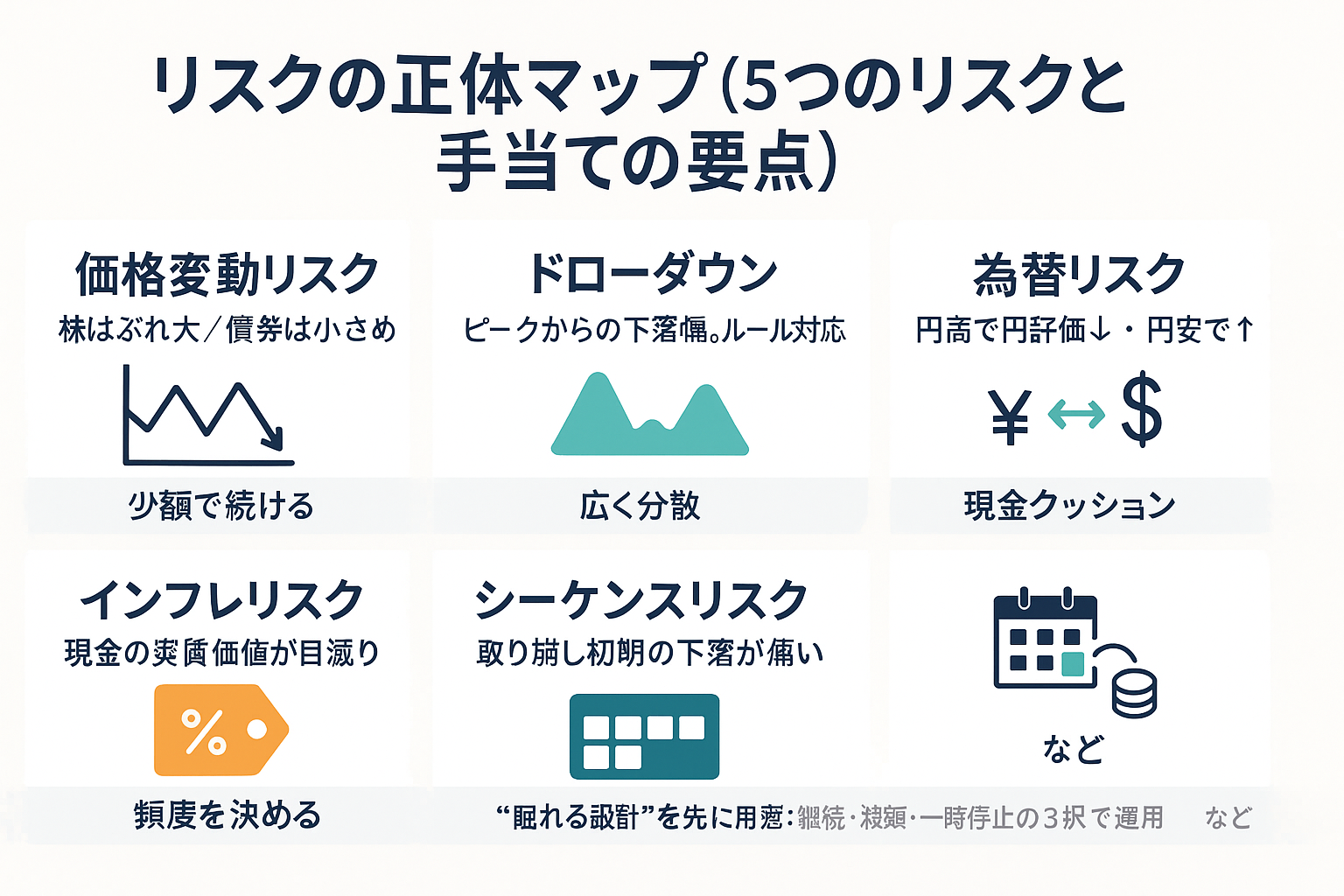
まず覚えること:リスク=“値動きのぶれ幅”。ぶれ幅が大きいほど、短期の上下はきつくなります。
- 価格変動のリスク
株式は上下のぶれが大きめ、債券は小さめ、現金はほぼ動きません。
→ 自分がどのくらいの上下なら落ち着いていられるかを先に決める。 - ドローダウン(いったんどこまで下がる?)
過去のピークからの下落幅のこと。心が折れる原因の筆頭。
→ 例:株式100%なら一時的に大きく下がることもある。数字に一喜一憂せず、ルールで対応。 - 為替リスク(円高・円安)
外貨に投資する投資信託は、円高で円評価が下がり、円安で上がりやすい。
→ 長期は通貨も分散&つみたて継続が基本。 - インフレリスク(現金の目減り)
物価が上がると、現金だけでは実質的な価値が減ることも。
→ 生活防衛資金を確保しつつ、低コストの投信で一部を運用。 - シーケンスリスク(取り崩し初期の下落)
取り崩しを始めた直後に大きく下がると影響が大きくなる。
→ 対策:現金1〜2年分のクッション/株比率を控えめに/定期・少額取り崩し。
✅ 安全運転のコツ
「最大どのくらい下がったら眠れなくなるか?」を考え、“眠れる配分”にしておく。
迷ったら睡眠テスト:「一晩で▲10%でも眠れる?」→NOなら株を減らす。
投資信託で実現する「分散投資の基本」
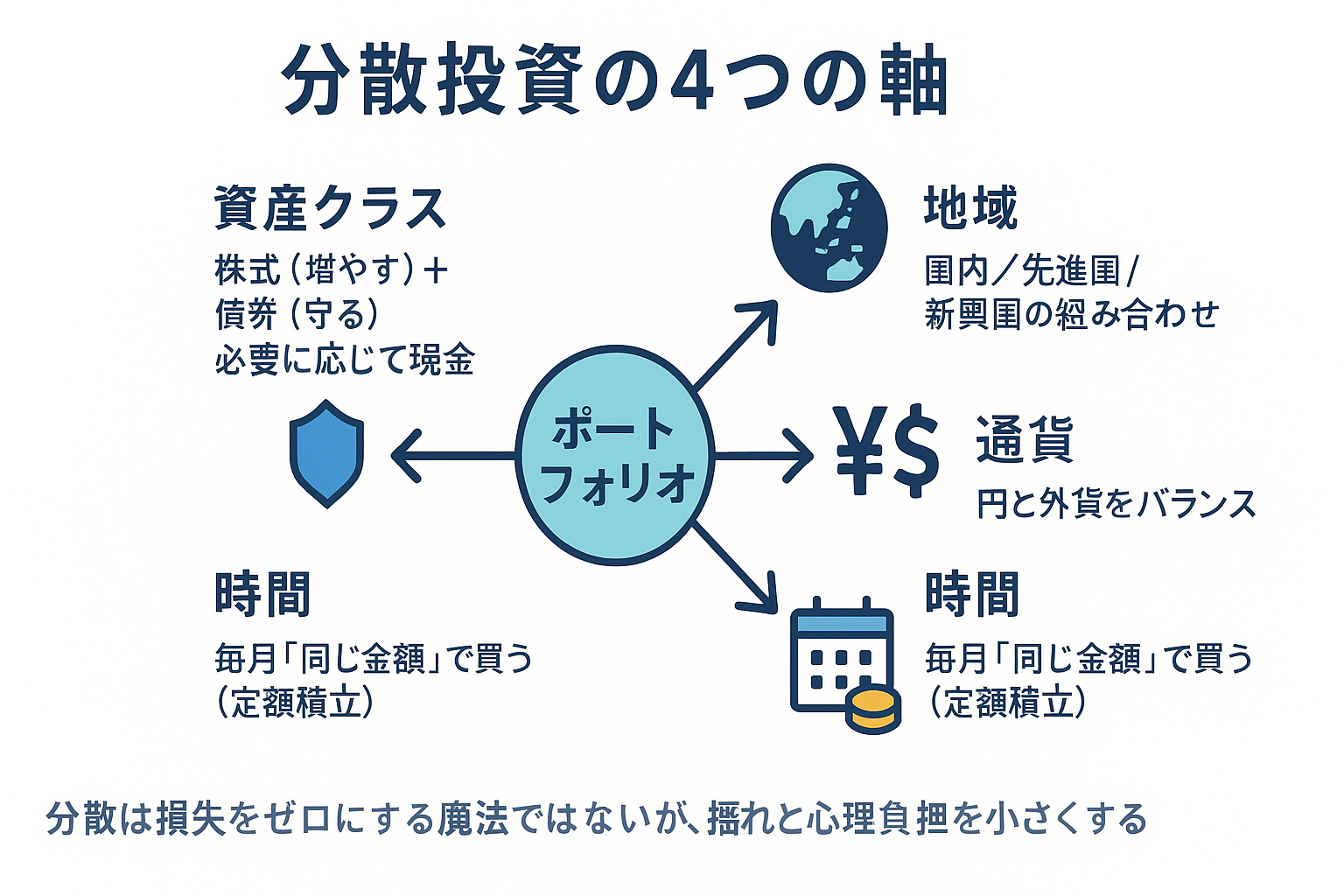
- 資産クラス分散:株式(増やす役割)+債券(守る役割)+必要に応じて現金。
- 地域分散:国内・先進国・新興国を組み合わせて地域的な偏りを減らす。
- 通貨分散:円と外貨をバランスよく持ち、為替変動の影響を分散。
- 時間分散:定期積立により購入価格を平準化。
※ 分散投資は損失を完全に避ける魔法ではありませんが、値動きの振れと心理的な負担を軽くしてくれます。
資産クラス分散:
- 株式インデックス(増やす役割)+債券インデックス(守る役割)+必要に応じて現金。
- まずは株式を全世界株 or 先進国株の投信1本からでもOK。債券はあとから比率を増やしていけば大丈夫。
地域分散:
- 全世界株インデックス1本なら自動で地域分散。
- 別構成にするなら「先進国株+国内株(+新興国は少額)」の組み合わせでもOK。
通貨分散:
- 円と外貨の通貨分散も、外貨資産に投資する投信で自然に実現。
- 長期の株式はヘッジなしがシンプル(外債は好みで一部ヘッジも可)。
時間分散:
- 毎月の自動つみたてで購入価格を平準化。価格は見すぎないのがコツ。
※ 分散投資は損失を完全に避ける魔法ではありませんが、値動きの振れと心理的な負担を小さくしてくれます。
はじめの一歩(例)
- 最小構成:全世界株インデックス投信 1本
- 少し拡張:先進国株 8:国内株 2 +(必要に応じて)先進国債券
- 見るポイントは ベンチマーク と 信託報酬(コスト) だけでOK。
今日から始めるチェックリスト
□ 使うベンチマークを決める(全世界株 or 先進国株 等)
□ 同じベンチマークの中で最安〜ほぼ最安の投信を1〜2本に絞る
□ つみたて額・日付を登録(給与日直後がおすすめ)
□ 同じ指数の重複がないかだけ最終チェック
次回は「積立投資とコスト最適化」について解説します。毎月の自動投資と低コストファンド選びで、”手間いらずの投資システム”を完成させましょう。
「学ぶ(入門・基礎)」トップに戻る↑
< 前の記事へ「用語と仕組みの基礎」
次の記事へ >「積立とコスト最適化」
(免責事項)本記事は投資助言ではありません。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。